不動産売却後の確定申告 手続きの流れや必要書類など基礎知識をわかりやすく解説
不動産を売却すると翌年に確定申告が必要となる場合があります。確定申告する機会が少ない会社員や公務員のなかには「方法がわからない」という人も少なくありません。本記事では不動産売却に伴う確定申告の方法を詳しく解説します。必要な書類や困った場合の相談先なども説明するので申告時の参考にしてください。
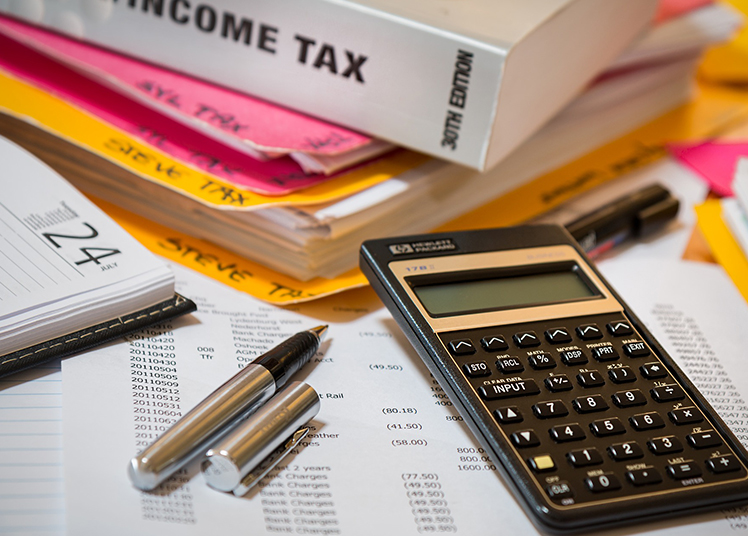
不動産売却を行った場合は確定申告が必要
マイホームなどの不動産を売却して利益が発生した場合、利益に対する納税額を確定させる必要があります。申告に必要なのは譲渡所得税で、そのための手続きが確定申告です。
確定申告は所得が会社などからの給料のみの人の場合、個人の代わりに会社が納税の手続きをしてくれます。そのため、会社員や公務員のなかには、自分で確定申告をしたことがない人も多いかと思います。一方、個人事業主の場合は、毎年確定申告する必要があります。
ただし、会社員や公務員であっても、不動産売却益など給与以外の所得があった場合は、個人事業主と同じように確定申告する必要があります。つまり、不動産売却を行った場合は、譲渡所得税の申告が必要となってくるのです。
確定申告では、まず1月1日から12月31日までの間に得た所得と、所得にかかる税金を計算します。税額が確定したら、翌年の2月中旬から3月中旬の間に所轄の税務署に申告し、納税しなければなりません。
この期限を過ぎてしまっていたり、そもそも申告を忘れてしまっていたりした場合は、無申告加算税と延滞税が課せられます。
無申告加算税は、原則として納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%が加算されます。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告した場合は、納税額に対して5%を加算した金額となります。
延滞税は、納付期限の翌日から完納するまでの期間に対してかかる税金です。なお、延滞税の計算方法の詳細については、国税庁ホームページ「延滞税の計算方法」で確認することができます。
確定申告の必要性に関する判断基準
不動産売却で得た利益は税法上において譲渡所得となり、譲渡所得税が課せられます。譲渡所得は、不動産売却で得た収入から取得費や譲渡するためにかかった費用を引いて算出します。計算した結果、売却益が発生した場合は確定申告しなければなりません。売却益が発生しなかった場合は、確定申告をする必要はありません。
ただし、不動産の売却で損失が発生した場合、その金額をその他の所得から控除することができます。控除によって所得の総額が少なくなると、その分、所得税も少なくなります。控除を受けるためには確定申告が必要です。
つまり、不動産売却で利益が発生した人、損失が発生して控除を受けたい人は確定申告が必要で、損失が発生しても控除を受けない人は確定申告が不要、ということです。(譲渡所得の計算方法と控除についての詳細は後述します)
課税方式は主に2種類
確定申告における所得の計算には、すべての所得と合算した課税所得に所得税の税率をかけて所得税額を計算する「総合課税方式」と、他の所得とは合算せず、所得ごとに決められた税率で所得税額を計算する「分離課税方式」の2つの方法があります。少し詳しく見てみましょう。
まず、所得は大きく10種類に区分されています。
| 種類 | 概要 | 課税方式 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 商・工業や漁業、農業、自由職業などの事業から生じる所得 | 総合課税 |
| 株式等を譲渡したことによる所得 | 分離課税 | |
| 不動産所得 | 土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得 | 総合課税 |
| 利子所得 | 国外で支払われる預金等の利子などの所得 | 総合課税 |
| 預貯金の利子などの所得 | 分離課税 | |
| 配当所得 | 株式の配当、法人から受ける剰余金の配当など | 総合課税 |
| 株式などの配当などで申告分離を選択した所得 | 分離課税 | |
| 給与所得 | 俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得 | 総合課税 |
| 雑所得 | 上記に該当しない所得。公的年金、非営業用貸金の利子など | 総合課税 |
| 株式等を譲渡したことによる所得や先物取引にかかわる所得 | 分離課税 | |
| 譲渡所得 | 乗用車(通勤・生活用除く)やゴルフ会員権などを売った所得 | 総合課税 |
| 土地や建物などを売った所得 | 分離課税 | |
| 一時所得 | 生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得 | 総合課税 |
| 保険・共済期間が5年以下の一時払い養老保険などの所得 | 分離課税 | |
| 山林所得 | 5年を超えて所有していた山林を売った所得 | 分離課税 |
| 退職所得 | 退職によって受ける所得 | 分離課税 |
総合課税方式
10種の所得のうち、事業所得や給与所得などは所得金額を合算して税額を計算します。これが総合課税方式です。税率は累進税率で、所得額が増えるにつれて5%から最大45%まで上がります。売却益がある場合には確定申告が必要で、譲渡所得がマイナスまたはない場合には確定申告が不要です。
なみに、10種の所得のなかに不動産所得が入っていますが、これは不動産の賃貸で得る所得のことで、不動産を売却して得た所得とは違うものです。
分離課税方式
総合課税には含まずに、所得ごとに決められた税率で税額を計算します。
不動産売却による譲渡所得は分離課税方式で計算します。また、10種類の所得のうち、山林所得、配当所得、退職所得なども、分離課税方式で税額を計算します。
これは総合課税方式が累進税率で税額を計算するため、所得の合計額が大きくなるほど税率も高くなるからです。そのため、不動産売却の利益を総合課税の所得と合算すると、単発的で一時的な所得であるにもかかわらず、税負担が大きくなってしまいます。これを防ぐために、不動産売却による所得は分離課税となっているのです。
総合課税方式と同じく、売却益がある場合には確定申告が必要で、譲渡所得がマイナスまたはない場合には確定申告が不要です。
不動産売却では「譲渡所得税」の確定申告を行う
不動産を売却した場合、譲渡所得にかかる譲渡所得税を確定します。
計算式は以下のとおりです。
譲渡所得には所得税と住民税が課税されますが、税率は、その不動産を所有していた期間が5年以下の「短期譲渡所得」か、5年超の「長期譲渡所得」かによって変わります。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% (所得税30% + 復興特別所得税0.63% |
9% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% (所得税15% + 復興特別所得税0.315%) |
5% |
※復興特別所得税は2037年までの所得税に対して2.1%課される税金です。
注意しなければならないのは、不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えていなければ長期譲渡所得にならない点です。
例えば、2016年6月から所有している不動産を2021年10月に売却した場合、実質的には5年を超えています。しかし、売却した年(2021年)の1月1日時点では5年以下ですので、短期譲渡所得になるのです。
保有する物件・土地の定期的な資産価値の確認がポイントです。
不動産売却の確定申告に関わる3つの特例
マイホームの3,000万円特別控除
マイホームの売却で発生した譲渡所得は、居住期間の長短にかかわらず、以下の条件を満たすことによって最高3,000万円まで非課税になる控除が受けられます。
・自宅として住んでいるマイホーム(居住用財産)
・マイホームとともにその敷地や借地権を売る
・マイホームを取り壊した場合は、譲渡契約まで土地を住居以外の用途にしていない
・売手と買手が親子や夫婦などの特別な関係でない
これらの条件を満たすと、売却益が3,000万円以内であれば、税金が発生しないということです。利用しやすい特例ですので、必ず確認するようにしてください。
これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
軽減税率の特例
3,000万円特別控除を適用しても譲渡所得がプラスになる場合は、軽減税率の特例を利用します。適用要件は売却した年の1月1日時点で所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合です。これを「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」といいます。
3,000万円特別控除の適用後の譲渡所得が対象となり、税率は以下のとおりです。
| 譲渡所得 | 所得税率 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 6,000万円以下 | 10.21% (所得税10% + 復興特別所得税0.21%) |
4% | 14.21% |
| 6,000万円超 | 15.315% (所得税15% + 復興特別所得税0.315%) |
5% | 20.315% |
※復興特別所得税は2037年までの所得税に対して2.1%加算されます。
譲渡損失の買換え特例
マイホームの買い替えのために住んでいた不動産を売却し、その際に損失が発生した場合は、居住用財産の譲渡である、売却価格が1億円以下であるなどの条件を満たすことによって、損失を他の所得から引くことができます。これを「損益通算」といいます。
また、損益通算で控除しきれなかった損失は、翌年から3年間にわたって繰り越すことができます。これを、「譲渡損失の繰越控除」といいます。損益通算を行うと、不動産売却による損失を給与や事業所得など他の所得から控除することができます。その結果、所得の総額が少なくなり、税金を抑えることができます。
会社員の場合は、月々の給料から所得税を引かれている人が多いはずです。売却の損失によって所得の総額が少なくなり、所得税額が少なくなった場合は、納めすぎた分が還付金として戻ってきます。
確定申告の際に必要となる計算
納税額を確定するためには譲渡所得の金額を計算します。
計算式では、最初に不動産の譲渡価額を算出し、そこから不動産を取得した時の費用などを引きます。
・譲渡価額:不動産の売却で得る収入
・取得費:売却した不動産を購入したときの購入代金と、購入時に支払った手数料など
・譲渡費用:不動産の売却時に支払う費用。仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、借家人に支払う立退料、建物の取壊し費用など
・特別控除:前述したマイホームの3,000万円の特別控除など
これらを計算すると、所得税や住民税を算出する譲渡所得が明らかになります。確定申告では、これらの金額を計算して「譲渡所得の内訳書」や「申告書第三表(分離課税用)」に記入します。
譲渡価額
まずは不動産の譲渡価額を計算します。譲渡価額は、売却価格に「固定資産税等精算金」を加えて算出します。
不動産を売却した売主は、引渡日以降の固定資産税等相当額を固定資産税等精算金という形で買主から受け取ります。
しかし、固定資産税は、1月1日時点の所有者が1年分を納税するものです。売主が受け取る固定資産税等精算金は、不動産の売却価格の上乗せ分と考えることができるため、固定資産税等精算金を売却価格に加えるのです。
ちなみに、マンションの売却時には管理費や修繕積立金を精算し、買主から精算金を受け取ることがあります。これは譲渡価額には含めません。
固定資産税が1月1日時点の所有者が納めるものであるのに対し、管理費などは一般的には引渡日以降は買主が負担するものですので、売主が前払いしている管理費などを買主から精算金として受け取っても、売主の収入とは見なさないのです。
取得費
取得費は、土地においては購入額、建物においては購入額から減価償却費を控除した金額を計算するのが基本です。譲渡価格から控除することができ、取得費が大きいほど譲渡所得が小さくなります。つまり、税負担が軽減されるのです。
また、取得する際、仲介手数料や立退料、移転料、搬入費や据付費、建物等の取り壊し費用などがかかった場合は、それも取得費に加えることができます。
減価償却費
建物の取得費は減価償却を計算します。
減価償却とは、取得から売却時までの間に経年劣化した価値の分を引くことです。減価償却を適用するのは建物のみです。土地は経年によって価値が変化することがないからです。そのため、建物の取得費についてのみ、建物の購入価額から減価償却費相当額を引きます。
減価償却費相当額は建物の購入価額の95%を限度として、所有期間が長ければ長いほど減価償却費相当額が大きくなります。
経過年数は築年数ではなく、購入から売却までの所有期間です。また、経過年数は、端数月がある場合、6カ月以上であれば1年として計算し、6カ月未満の端数月は切捨てます。
減価償却費は支出を伴わない経費です。経費ですので会計上費用として計上することができます。つまり、経費を差し引いた分、利益が小さくなりますので、税負担が軽減されることにつながるのです。 償却率は建物の構造(木造、鉄骨蔵、鉄筋コンクリート造など)によって数値が定められています。
| 構造 | 非事業用の 償却率 |
耐用年数(※) | |
|---|---|---|---|
| 木造 | 0.031 | 33 | |
| 木骨モルタル | 0.034 | 30 | |
| 鉄骨造 | 骨格材の肉厚が3mm以下 | 0.036 | 28 |
| 骨格材の肉厚が3mm超4mm以下 | 0.025 | 40 | |
| 骨格材の肉厚が4mm超 | 0.020 | 51 | |
| 鉄筋コンクリート造 鉄筋・鉄骨コンクリート造 |
0.015 | 70 | |
※非事業用資産の耐用年数は事業用資産の1.5倍で計算
概算取得費
建物を取得した時期が昔などの理由から、取得費がわからないときは概算取得費として、売却金額の5%相当額が取得費となります。また、取得費がわかっている場合でも、実際の取得費が売却金額の5%相当額を下回る場合は、売却金額の5%相当額を取得費とすることができます。
不動産売却があった場合の確定申告で必要な書類
確定申告書B
確定申告書Bは、不動産所得や事業所得がある人などが確定申告に使う一般的な書類で、税務署で入手できます。
分離課税用の申告書
前述したとおり、不動産売却の利益は分離課税です。総合課税である給与所得などと分けるため、分離課税を申告する分離課税用の申告書で納税額を申告します。この申請書も税務署で入手できます。
譲渡所得内訳書
土地や建物の譲渡による譲渡所得金額の計算用として使用するのが、譲渡所得の内訳書です。この書類も税務署で入手できます。または税務署のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
| 必要書類 | 入手場所 |
|---|---|
| 確定申告書の用紙(申告書B、申告書第三表/分離課税用) | 税務署 |
| 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表と計算明細書) | 税務署 |
| 戸籍の附表(売却後2カ月経過後にされたもの) | 売却不動産がある市区町村 |
不動産売買契約書
売却する物件の購入時と売却時の不動産売買契約書を準備します。契約書が必要なのは、購入、売却の金額が申告どおりであることを証明するためです。契約書はコピーで構いません。注文住宅を売却した場合は、建築当時の請負契約書が必要です。
登記事項証明書
不動産を売却すると、不動産の所有者が買主に移転し、その内容が登記されます。登記事項証明書は、その内容を印刷したものです。登記事項証明書は近くの登記所で入手でき、オンラインで申請することも可能です。
領収書
不動産会社に支払った仲介手数料や登記費用などの領収書を準備します。領収書は、売却した不動産の取得や譲渡にかかった費用を証明するためのもので、コピーで構いません。固定資産税の清算書や登記費用などの領収書がある場合は、それらも準備しておきましょう。
| 不動産取得時 | 仲介手数料の領収証 |
|---|---|
| 登記費用など諸費用の領収証 | |
| 不動産売却時 | 売買契約書と領収証 |
| 仲介手数料の領収証 | |
| 測量費・登記費用など諸費用の領収証 |
確定申告の流れ
適用される特例を確認する
まずは売却した不動産について、利用できる特例があるか確認します。特例は利用するための条件があり、マンション・土地・戸建てで必要書類が異なりますので、国税庁のウェブサイトなどで条件の内容を確認しましょう。
譲渡所得税額を計算する
課税対象となる譲渡所得の金額を計算します。譲渡所得がプラスの場合でも、特例を使うことによって所得がゼロになったり、納税額が少なくなったりする場合があります。
譲渡所得税額の計算式
譲渡所得の計算式は以下のとおりです。取得費は、建物の取得費の減価償却を忘れずに計算しましょう。
確定申告書を作成する
確定申告書を作成します。
確定申告書は税務署でもらうことができますが、国税庁のウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」でオンライン申告することもできます。
オンライン申告は入力する金額を自動で計算してくれるため、手書きよりも便利です。記入や入力方法がわからなくなった場合も、このページ内に操作方法などに関する問い合わせ専用窓口が設けられていますので、電話で確認することができます。
手書きでの記入時の注意点
手書きする場合、申告書は複写式なので黒のボールペンで強めの筆圧で書くようにしましょう。鉛筆は使用できません。
数字などを書き間違えた時には、間違えた数字に二重線を引き、上下の空いている欄に正しい数字を書き込みます。記入漏れなどがないことを確認したら、最後に印鑑を押して完成です。印鑑を押していないと再提出になるので注意してください。
確定申告書を提出する
確定申告書は期日までに提出します。
提出方法は、税務署に持っていく、郵送する、データを送る(e-Tax)の3つがあります。
記入方法などについてわからない点がある場合は、税務署に持っていき、その時に確認することができますが、例年、確定申告の時期は税務署が混み合います。提出の時間がかかり、密になりやすいため、自分で記入できた場合は郵送かe-Taxを利用するのが良いでしょう。
郵送する場合は、手書きした確定申告書か、国税庁のウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」で作成した確定申告書を出力し、所轄の税務署に送ります。
e-Taxは、「確定申告書等作成コーナー」で作成した確定申告書をそのままオンラインで所轄の税務署に送付します。
e-Taxは税務署の開庁時間を問わず、24時間いつでも申請書を送ることができるのがメリットです。e-Taxで申請するためには、近くの税務署で、IDとパスワードを発行してもらう必要があります。
まとめ
確定申告は、不動産を売却する人にとって非常に重要な手続きです。確定申告する機会が少ない・したことがない会社員や公務員のなかには、難しいと感じる人も結構いるかもしれません。しかし、本記事を参考に確定申告の流れに沿って必要書類や基本知識を把握して進めていけば、決して難しい手続きではありません。
ただし、不慣れな人が多く、記入漏れやミスが起きやすい手続きでもあります。正確に申告するために、不明点などを1つ1つ確認しながら進めていきましょう。わからない・不明な点があれば、売却を依頼する仲介会社の担当者が書き方のポイントなどを聞いてみるのもいいでしょう。売却後も手厚く支援してくれる会社を選ぶことも確定申告を円滑に行うためのポイントです。
保有する物件・土地の定期的な資産価値の確認がポイントです。
| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、当社の見解を示すものではありません。 |
| ・ | 本コンテンツに掲載の情報は執筆時点のものです。また、本コンテンツは執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び当社が保証するものではありません。 |
| ・ | 本コンテンツは、情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の取得・勧誘を目的としたものではありません。 |
| ・ | 本コンテンツに掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、当社は一切責任を負いません。 |
| ・ | 本コンテンツに掲載の情報に関するご質問には執筆者及び当社はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 |









