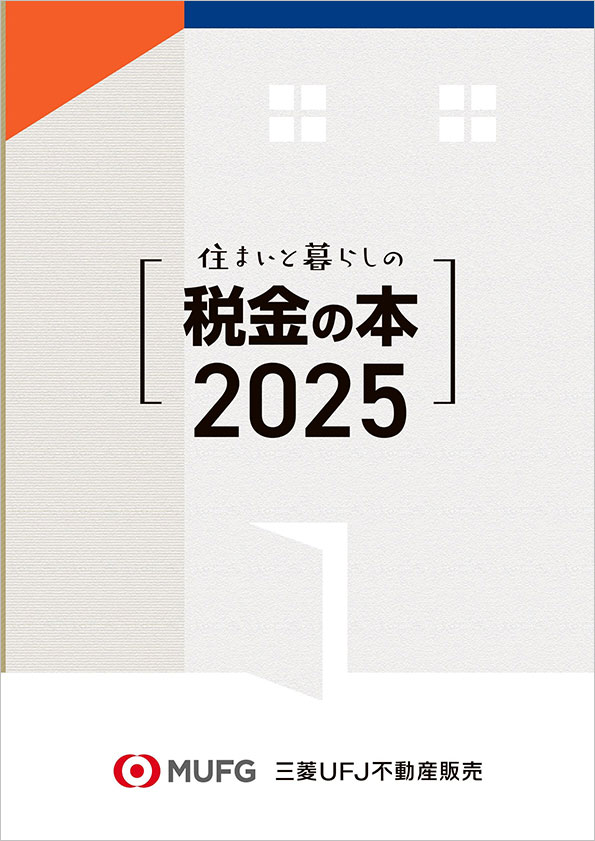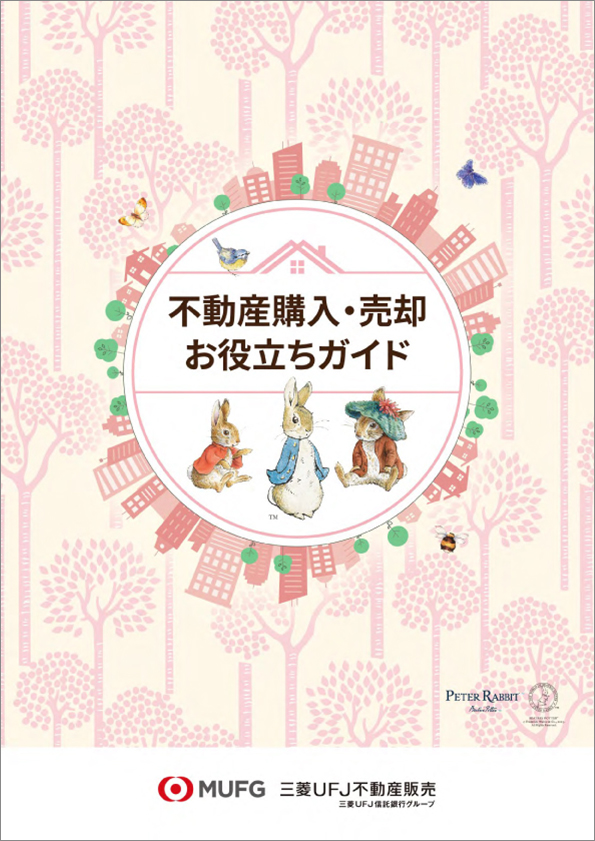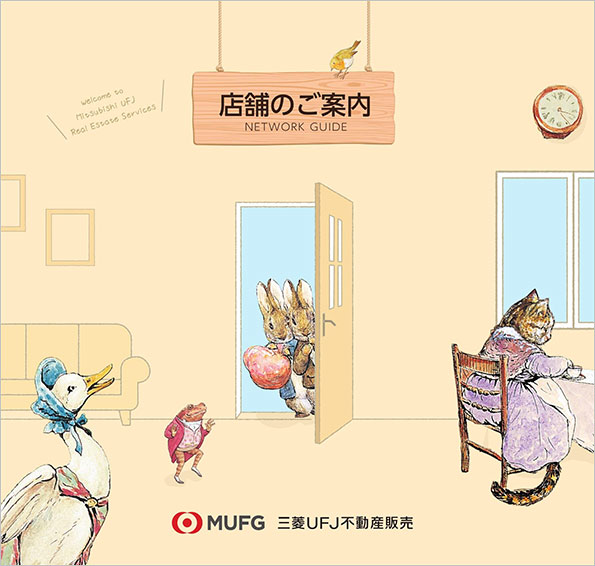電子ブック
画面上で電子ブックをご覧いただけます。ご覧いただきたい電子ブックをクリックしてご覧ください。
-
住まいと暮らしの税金の本(2025)
01:マイホームの税金の特例
02:マイホームの資金計画の税金
03:マイホームを購入するときの税金
04:マイホームの住宅ローン減税
05:マイホームを保有しているときの税金
06:マイホームを売却するときの税金計算と特例
07:非居住者(海外転勤者、外国人)の不動産の税金
08:不動産の相続と相続税
09:賃貸不動産経営の税金
10:不動産の消費税
11:税率表・計算資料
12:申告・申請・納税必要書類
●電子ブックを見る -
不動産購入・売却お役立ちガイド
■購入編
■売却編
■住まい1活用ガイド
■購入・売却活用編
■買い替え編
■Q&A
■お引越しチェックリスト
■住まい1会員向けサービス(無料)
●電子ブックを見る -
不動産投資お役立ちガイド
01:不動産投資の基礎
02:不動産投資のはじめ方
03:不動産投資のはじめ方
04:コストについて
05:物件購入の流れ
06:確定申告のポイント
07:相続対策
08:不動産投資イメージ
09:事業承継
10:資産の組み換え
●電子ブックを見る -
サポートサービスガイドブック
・三菱UFJ不動産販売の仲介サービス
・サポート・サービス紹介
・サービス運用一覧表
・よくあるご質問
・プロフェッショナルをご紹介
・住まい1会員向けサービス(無料)
●電子ブックを見る -
店舗のご案内
・首都圏:23センター
・名古屋:4センター
・関 西:7センター
・サービスのご案内
●電子ブックを見る -
コーポレートプロフィール
・信頼と安心の理由
・三菱UFJ不動産販売の経営ビジョン
・MUFGグループであること
・お客様の声を聞き、ニーズに応えること
・組織力と人材力で、満足度を高めること
・ごあいさつ
●電子ブックを見る
住まい1デジタルガイドブック便利な機能について
住まい1デジタルガイドブックはガイドブック内のワード検索をすることができます。知りたいワードなど画面下の検索ワードボックスにテキストを入力してご利用ください。
店舗のご案内
各種不動産に関するお問い合わせにつきましては、営業担当者までお気軽にご連絡ください。